「ずっと座ったままだから、なんだか腰が痛い⋯」
「デスクワーク中心の生活で運動不足⋯」
「なんか同じ姿勢のままだと集中力がなくなるんだよね⋯」
在宅ワーカーなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか?
とはいえ、目の前の仕事を止めるわけにはいきませんよね。
そんな方に向けて、今回ぜひ紹介したいのは「昇降デスク」です。
「今さら昇降デスクなんて、もう知ってるよ!」
そんな声が聞こえてきそうですが、実際に私は3年以上昇降デスクを使い続けています。
これを導入することで、座ったまま仕事を続けるよりメリハリがついて、健康的に仕事ができていると実感できました。
「健康的で快適に作業できる方法」を知りたい方は、この記事内容を参考にして作業環境を見直すヒントにしてみてください。
デスクワーク時の身体の不調、心配ごとがつきまとう日々から抜け出せるきっかけになれば幸いです。
昇降デスクのメリット:健康・作業効率アップ
①同じ姿勢で作業しなくて良い
昇降デスクを使えば、座って作業し続けなくてはならない、なんてことはありません。
好きなタイミングで机の位置を高くして、立ったまま作業ができます。
「これで運動不足が解消できる!」と考え、ずっと立ったままで作業しようとする方もいらっしゃるでしょう。
気持ちは分かりますが、ちょっと待ってください!
使い始めたばかりのときは、まだ慣れていないこともあり、足が疲れてしまいます。
それだと、立って作業するのが嫌になってしまうかもしれません。
「昇降デスクのメリット=立って作業ができる」と思いがちです。
ですが、一番のメリットは「作業する姿勢を変えられること」なんです。
パソコン作業の時間が長ければ長いほど、このメリットが大きいですね。
②メリハリをつけて作業できる
①と関連しますが、私の場合、同じ姿勢を続けていると集中力が落ちてしまうことがあります。
そこでタイマーを使って、「この時間は座ったまま」「一定時間経ったら立って作業する」というのを繰り返しています。
例えば、「30分座って作業したあとは、15分立って作業」といったスタイルです。これで1日の座っている時間がおよそ半分になりました。
タイマーを使わないと、どうしても同じ姿勢でずっと作業してしまいがちなので、意識して区切りをつけるのは効果的です。
こうすることで、メリハリのある作業スタイルを維持できます。
③ 高さ調整ができる
机の高さを調整できることで、自分にとって最適な姿勢で作業することが可能です。
一般的な机の場合、ほとんどは椅子だけが高さ調整できる仕組みですよね。
しかし、座った状態のままでも、椅子に加えて机の高さも変えられるとなると、より自分に合った姿勢を保つことができます。
私にとっては、これが実はうれしい「おまけ要素」だったりします。
昇降デスクのデメリット:組み立て・解体がめんどう
デメリットとして挙げるなら、昇降デスクの「組み立て」と「解体」がめんどうだという点です。
一度組み立ててしまえばしばらく使い続けられますが、引越しなどで解体が必要になると大変です。
私自身、昇降デスクを使い始めてから転居しましたが、そのたびに解体と組み立てをするのはとても手間でした。
具体的に何が手間かというと、大きく2つあります。
1つ目は安全性の面、2つ目は時間がかかるという点です。
1. 安全性について
組み立ての際は、まず天板を床に置いて脚部を取り付けます。
脚部がそこそこ重いので、もし倒れたりすると床に傷がついてしまう可能性があります。
さらに、脚部を取り付けた後は、天板をひっくり返して持ち上げる必要があるため、慎重に作業しなければなりません。
ちなみに私が使っている昇降デスクは、総重量が約39.5kgあり、脚部だけでも重さを感じます。
フローリングの上で直接組み立てるのではなく、じゅうたんでも良いので、何かシートの上で作業するのが良いでしょう。
2人で組み立てることをおすすめします。
2. 時間がかかる
私の場合、2人がかりで作業してもトータル1時間ほどかかりました。
ネジや部品、機械のパーツが25個ほどあり、それぞれを探して取り付けるのがややストレスでした。
ただ、一緒に組み立てを手伝ってくれたのが、ものづくり好きの人だったのは幸いでした。
DIYやものづくりに抵抗がない方にとっては問題ないかもしれませんが、そうでなければ退屈に感じたり、集中力が切れてさらに時間がかかったりする可能性があります。
この2点の対策として、ネットショッピングで昇降デスクを購入する場合、組み立てオプションを利用できる場合があります。
追加費用はかかりますが、組み立てが苦手な方は検討しても良いでしょう。
私の使用環境:デスク周りのセッティング
私が使っている昇降デスクは、天板の幅が120cmあります。
中央に24インチのモニター、左側に23インチのモニター、右側にMacBookを配置しており、幅120cmを目一杯に使い切っています。
奥行きが70cmあるのですが、モニターを複数並べると画面との距離がやや近いと感じることがあります。
幅に関しては120cmで問題ありませんでしたが、奥行きはもう少し余裕があったほうが使いやすかったと感じています。
特に、私は3画面を横に並べているため、左右どちらかの画面を見る時間が長くなると首を傾けた姿勢が続き、首に負担がかかる感じがします。
基本的にモニター1〜2台であれば、奥行き70cmでも十分だとは思いますが、3台以上使う場合はもう少し奥行きがある昇降デスクを検討するとよいでしょう。
ただ、サイズが大きくなるに従って金額も上がるので予算オーバーしないかご注意ください。
使ってみた感想:3年以上のリアル体験レビュー
購入当初から振り返ってみても、やはり昇降デスクは「買って良かった」と思っています。
一時期は机の高さを上げるのが面倒に感じることもありましたが、そんなときは席を離れて軽いストレッチをするなど工夫していました。
今ではタイマーで時間を区切り、座って作業する時間と立って作業する時間を明確に分けることで、メリハリをつけて活用しています。
もし今使っている机がなくなり、新たに机を用意しなくてはならなくなったら、私は迷わず再び昇降デスクを購入するでしょう。それくらい重宝していて、仕事をするうえで欠かせない存在になっています。
昇降デスクには手動式と電動式がありますが、私の場合は電動式を選んで正解でした。
ボタンひとつで設定した高さまで調整してくれるため、本当に楽です。
1日に何時間も作業する場合、昇降の回数も自然と増えるので、毎回ハンドルを回す手間がないのは大きいですね。
さらに昇降時の音も静かなので、全くストレスに感じません。
ただ、デメリットでも触れたように、引越しの際には解体が必要になるので、そこはネックです。その他に関しては文句なしで満足しています。
昇降デスクの選び方
昇降デスクを選ぶうえで、最も重視したいのはやはりサイズです。
あとは、メーカーやデザインなど、個人の好みに合わせて判断すれば問題ありません。
参考までに、私が使っている昇降デスクの仕様は以下のとおりです。
・幅:120cm
・奥行き:70cm
・高さ:71~117cm
・耐荷重:80kg
・重量:39.5kg
幅
設置するモニターやPCの種類・台数に合わせて決めるのが良いでしょう。
奥行き
最低でも70cmはあったほうが無難です。
60cmだとノートパソコン1台なら問題ありませんが、モニターなどを複数台設置する場合は画面との距離が近く感じるかもしれません。
70cm以上あると安心です。
高さ
できるだけ広い昇降範囲をもつ製品がおすすめです。
そのほうが自分に合った快適な作業ポジションを見つけやすく、「あと1cm低くできたら…」「もう1cm高ければ…」といった後悔がなくなります。
メモリー機能
設定した高さを登録できる機能です。
座り作業用・立ち作業用・予備用など、3つ以上登録できると便利でしょう。
まとめ|健康的に仕事できる環境を手に入れよう!
少しでも快適な状態で作業するための方法として、「昇降デスクの活用」をメリット・デメリットの両面から解説しました。
メリットとして、
・同じ姿勢で作業しなくて良い
・メリハリをつけて作業できる
・高さ調整ができる
デメリットとしては、「組み立て・解体がめんどうなこと」です。
在宅ワークの働き方は、今後ますます定着していくでしょう。
そのため、長期的に見たときに昇降デスクへ投資することは選択肢として十分に検討の余地があると思います。
もし、昇降デスクに興味をもったのであれば、今回の記事を参考にご自身に合った昇降デスクを選んでみてください!
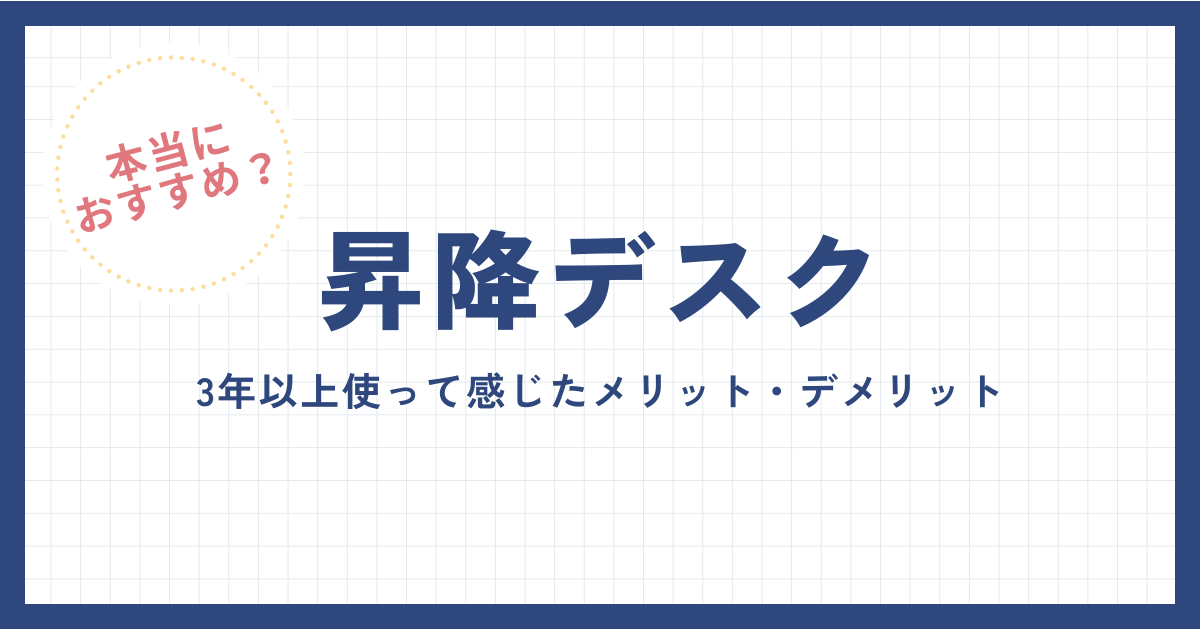
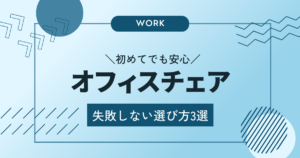
コメント